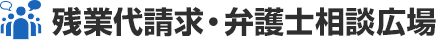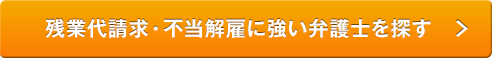労災隠しは違法!被害に遭った時の対処法は

汚職や談合、贈収賄に情報隠蔽等、企業による犯罪行ためは昔から存在します。もちろん企業の不正は許されませんが、そうした中でも「労災隠し」は労働者に直接的な影響があるため、看過できない問題と言えます。そこで今回は、労災隠しの実態や被害に遭った際の対処法等を、法律的観点から具体的に解説していきます。
労災隠しとは

脱税や助成金の不正受給にリコール隠し等、いつの時代も企業による犯罪行為は絶えません。そして今回紹介する「労災隠し」もそんな企業不正の一つです。労災、つまり労働災害が発生した際、使用者側がその事実を隠蔽するのです。そもそも労働災害とは何なのでしょうか。まずはその具体的な定義を押さえた上で労災隠しについて解説していきます。
そもそも労働災害とは
労働災害とは負傷や、疾病、及びそれによる後遺症、死亡等、労働の過程で労働者自身が被った災害を言います。区別する国もあるものの、通勤中の災害も含むのが世界的標準になっています。
労働災害の定義
定義については労働安全衛生法第2条で「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう」とされています。労働災害は建設業や製造業、運搬業、化学工業等、危険と隣り合わせの作業を伴う業種に突出して多く、有名なものとしては粉塵爆発によって458名の死者と839名の一酸化炭素中毒者を出した「三井三池三河炭鉱粉塵爆発事故」や現在も数えきれない程の患者が後遺症に苦しむ1960年代から80年代に広く使用されたアスベストによる健康被害「アスベスト被害」等が挙げられるでしょう。
労災関連の規定が複数ある
労働災害関連の法律としては労働基準法の他、職場における労働者の安全と健康を守り、労働災害を防止することを目的に労働者の安全と衛生についての基準を定めた「労働安全衛生法」や、労災の被災者を保護すること等を目的に必要な給付をすることを主に定めた「労働者災害補償保険法」、適正な作業環境を確保し労働者の安全を図る目的とした「作業環境測定法」等が存在します。
労災隠しとは
労災隠しとは会社が労働基準監督署への報告を怠る、又は虚偽の報告をすることです。この様な行ためは法律違反で、発覚すれば労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となります。
労働災害が起きた時使用者が保証しなければならない
労働災害において、使用者は被災労働者や遺族に対して損害賠償責任を負うことがあります。労災申請の手続きが煩雑で手間がかかる、或いは会社が無知であると言った理由に加えてこうした賠償金の支払いを免れるために使用者が労働災害の事実を隠す行為を「労災隠し」と呼びます。
労働災害か否かの判断が難しいケースも多い
また一口に労働災害と言っても「業務遂行性」のものと「業務起因性」のものに分かれます。前者は“使用者の支配管理下で就業している状態での死傷病”を指し、業務中にトイレに行った際の怪我や休憩中の災害、出張先での宿泊中の怪我等が該当します。しかし事業場外で、業務とはいえない活動に従事しているときには、業務遂行性が認められないと考えられます。
例えば、参加が任意の会合に出席した際の事故等では業務遂行性は認められません(東京地裁判決平成11年8月9日)。後者には“事業主の支配下での業務に起因した災害による死傷病、つまり業務と一定の因果関係がある死傷病が分類されます。しかしこうした基準をもってしても労動災害か否かを判断することが困難なケースも多いのです。
労災隠しに遭うと本来は受けられる保障がされない
労働者は本来労働災害に遭ったら、「労働者災害補償保険」が適用され、治療費は全額保障され、被災により労働ができなくなった場合も賃金の6割の収入保障を受けられます。しかし労災隠しをされた場合、治療費は全額自己負担、収入保障も受けられないのです。また労災保険が適用されれば受けられるはずの後遺症や死亡時の遺族に対する保証も労災隠しに遭った場合は、ありません。
なぜ労災隠しは蔓延っている?

労働災害は被災した従業員はもちろん、その家族の生活にまで大きな影響を与えることがあります。労働災害が発生した場合、使用者は直ちに労働基準監督署に労災の届け出をしなければなりませんがそれを怠る労災隠しが次々と発覚しています。ではなぜ労働隠しが行われるのでしょうか。
労働災害に帰する責任を免れるため
労働災害が発生した場合、使用者側は「刑事責任」「行政責任」「民事責任」「社会的責任」の4つの責任を問われることになりらす。これらを逃れるために労災隠しが行われるのです。
死亡災害等の重大な労働災害が発生すると、労働安全衛生法に基づいて労働基準監督署による捜査が行われます。違反が発覚すると、刑事責任を追及されることになります。加えて、警察関係者による捜査も行われます。業務上の注意を怠って従業員を死傷させた場合には、刑法の業務上過失致死傷罪に問われ懲役5年以下または100万円以下の罰金刑に処されます。
また、事業者への立ち入り捜査の際、違反が発覚すれば是正勧告や作業停止命令等の行政処分も受けます。指示に従わない場合は,営業停止、国や地方自治体の競争入札への参加停止(指名停止)といった行政処分を受ける可能性があります。労働災害が起きれば事業者は経営面でも大きな痛手を負うことになります。
労働災害において使用者に安全配慮義務違反や不法行為等があった場合、使用者は被災労働者や遺族に対して損害賠償責任を負います。
労働災害が発生すると、各メディアで会社名と共に報道されることがあります。特に状況が劣悪だった場合、会社は批判の矢面に立たされ、ブラック企業として非難されます。殊近年ではネットによりあっという間に悪評は広まり、企業の信頼は地に落ち、それが従業員の離職や経営難等に繋がり、最悪倒産することにもなり兼ねません。
労災保険のメリット制度
労災保険は“メリット制度”をとっています。これも労災隠しがなくならない大きな要因の一つです。
事故があれば保険料が上がる仕組みのために労災を隠ぺいする
メリット制度とは、事が起こらなければ保険料は下がりますが、逆に有事、つまり労動災害がある程、保険料が上がる仕組みです。自動車保険と同じ仕組みですがこの保険料は事業所側が100%を払っているため、労働災害が発生しても「なかったことに」しよう、ということになるわけです。
現場の構図の問題
さらに、労災隠しは仕事の受注の構図も大きな背景としてあります。
例えば労働災害の発生率が高い建設業界では、労災隠しが特に横行しています。こうした現場においては現地で作業を行う“下請け”が労働災害を起こしても“元請け”の労災保険を使わなければなりません。また労働基準監督署による調査が入り、重大な事故として送検されれば公共工事における一定期間の指名停止等のペナルティが課せられることもあるのです。
入札ができなくなることは公共工事に依存する企業にとって大ダメージでしょう。加えて補償問題等で下請けが提訴された時には元請けに責任があるとされるケースも多く、飛び火を受けたくない元請け業者は労働災害を起こした下請けとの取引を中止します。そしてそうならない様に、下請けは必至で労災隠しを行う訳です。また現場で事故が発生したり、労働基準監督署から「是正勧告書」や「使用停止等命令書」を交付されると、会社によっては賞与カット等のペナルティを科しているため、元請けも一緒になって労災隠しを行うケースもあるのです。
労災隠しの実態|労働隠しへの対処法は?

しかしながら、こうした事情を全て加味しても、企業にとって労災隠しは分が悪いと言えます。その場はしのげても後々内部告発等によって労災隠しが発覚する確率は極めて高く、そうなった場合の企業の信頼の失墜は労働災害によるそれの比ではありません。では労災隠しに遭った場合、従業員はどうすればよいのでしょうか。最後にありがちな労働隠しのケースや、その対処法等を解説します。
よくある労働隠しのケース
労働災害として処理したくないがために、嘘をついてごまかしたり、口止め料を払って労災隠しをするケースが多いです。
治療費等を会社で受け持つ代わりに内密にするように求める
ケガの治療費等、事故による損害を会社側で負担することと引き換えに労働災害を申告しないように言われるケースは非常に多くあります。もちろん、会社がケガや病気が完治するまで補償してくれる保証はどこにもありません。
労働災害になるのは正社員のみであると主張してくる
また正社員でなければ労働者災害補償保険の対象にならず、保険金が下りないと主張してくるケースも頻繁に見受けられます。しかしこれは間違いで原則として労災保険は正社員だけでなく、パートタイマーや、有期契約労働者等を含む全ての労働者に適用されます。
労災隠しに遭った時の対処法は
では労災隠しに遭った場合や労働災害を疑った場合、従業員がとるべきはどのような行動なのでしょうか。
労働基準監督署に届け出る
会社が労災を認めてくれない場合、まずは労働災害に遭った旨を労働基準監督署に申し出ましょう。その際、事故の経緯や疾病の状況、会社の対応等を相談前に整理してまとめておくと良いでしょう。
治療の際は労災保険しか使えない点に注意
労働災害の治療に使えるのは労働保険のみである点に注意しなければなりません。私生活でけがや病気をした時と同じ様に健康保険や社会保険を使うと違法になります。会社がその様に勧めてくる場合もありますが、応じた場合詐欺行ために加担することになります。
泣き寝入りせずきちんと届けることが大切
労働災害に遭った時は、泣き寝入りするのではなく、きちんと労働基準監督署に届け出ることが大事です。事故の原因を明らかにすることが以後の被災者を出さないためにも大切と言えるでしょう。
関連記事一覧
 有給休暇について押さえておくべきこと|法的観点から解説しました
2026.02.20200,876 view
有給休暇について押さえておくべきこと|法的観点から解説しました
2026.02.20200,876 view パワハラとはどういうもの?パワハラの実態と対処法
2026.02.20179,884 view
パワハラとはどういうもの?パワハラの実態と対処法
2026.02.20179,884 view 変形労働時間制の定義と残業代の計算方法~対象期間による違いとは?
2026.02.2022,638 view
変形労働時間制の定義と残業代の計算方法~対象期間による違いとは?
2026.02.2022,638 view 労働時間の定義|「労働時間」に含まれるモノと含まれないモノ
2026.02.2077,139 view
労働時間の定義|「労働時間」に含まれるモノと含まれないモノ
2026.02.2077,139 view 会社にタイムカードの開示義務はある?タイムカードの保管期限は3年!
2026.02.2034,993 view
会社にタイムカードの開示義務はある?タイムカードの保管期限は3年!
2026.02.2034,993 view 会社都合退職とは?自己都合退職と違い転職や福利厚生でメリットがある
2026.02.2026,058 view
会社都合退職とは?自己都合退職と違い転職や福利厚生でメリットがある
2026.02.2026,058 view 知っておきたい退職の準備と退職後の手続き
2026.02.209,570 view
知っておきたい退職の準備と退職後の手続き
2026.02.209,570 view セクハラを受けたらどういたらいいの?その実態と対処法
2026.02.2051,735 view
セクハラを受けたらどういたらいいの?その実態と対処法
2026.02.2051,735 view 会社が雇用保険や社会保険に入ってくれない場合、どうする?
2026.02.20285,579 view
会社が雇用保険や社会保険に入ってくれない場合、どうする?
2026.02.20285,579 view 裁量労働制を実施している会社に就職・転職するときの注意ポイント
2026.02.208,764 view
裁量労働制を実施している会社に就職・転職するときの注意ポイント
2026.02.208,764 view